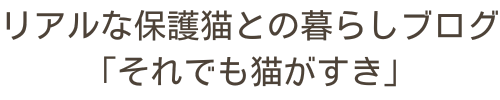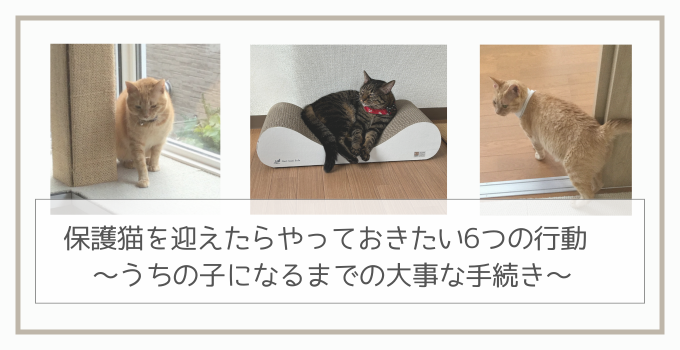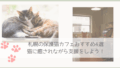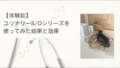保護猫を迎える準備は、猫用のグッズを揃えたり、部屋を整えたりするだけではありません。
「うちの子」として新しい家族を迎えるにあたっては、事務手続きはもちろんのこと、健康面についても注意が必要です。
今回は、私が2代目猫を迎えたときの体験をもとに、猫を迎える前に知っておきたいポイントについてまとめました。
本記事が「猫を出迎える準備」の段階でお役に立てればうれしいです。
保護猫を迎えたらまず行動すべきこと
大きく分けると「事務手続き」と「動物病院の受診」に分かれます。
保護団体から譲渡した場合は、事務手続きは多岐に渡り渡ります。そして、猫の健康状態によっては、直ちに受診が必要になることもあります。
いざという時に落ち着いて行動できるように、猫を迎えたらやるべきことを「6つの行動」に分けてご紹介していきます。
2.保護時代にかかった費用と支払内容を確認する
3.マイクロチップの有無と登録手続きについて
4.ワクチン接種歴の証明書を確認する
5.動物病院にかかる前に考えておきたいこと
6.まずは動物病院で健康診断を受けよう
それでは順番に確認していきましょう。
1.契約書の内容をしっかり確認・理解する
どこの保護施設でも、猫を譲渡する際には必ず契約書を交わします。契約書には主に、トライアル期間や正式譲渡に関する内容が記載されています。
・猫が新しい環境に馴染めるか
・猫の健康状態に問題がないか
・里親と猫との相性はどうか
など、これから猫との関係性を築くための大切な期間となります。
期間は保護施設によって異なり、1週間程度から2週間程度が一般的です。
特に先住猫がいる場合は、猫同士の相性も確認する必要があります。猫はストレスに弱いので、トライアル期間中は体調や行動を観察し、気になることがあれば保護施設に相談しましょう。
2.保護時代にかかった費用と支払内容を確認する
医療費やワクチン接種、去勢・避妊手術などを含め、保護猫を迎える際には費用を支払うのが一般的です。
わが家の場合は、初代猫の時は20,000円、2代目猫の時は30,000円を支払いました。
後から初代猫の個人保護主さんに聞いた話では、猫の空輸代を請求する方もいるようです(初代猫のハーにゃんは、空輸を経てわが家に来た経緯があります)
特に個人で保護活動をされている方は、独自のルールを設定している場合もあります。後でトラブルにならないよう、事前に費用の内訳や支払い内容を確認しておきましょう。
日用品に医療費に…猫を迎えたら初期費用って、いくらになるの?
気になる方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
▷ 【実体験】保護猫の初期費用はいくら?約15万円かかった内訳と節約のコツ
3.マイクロチップの有無と登録手続きについて
ペットショップで販売される犬猫にはマイクロチップの装着が義務付けられていますが、保護猫には必ずしも装着されているとは限りません。
もし迎えた猫がマイクロチップ装着済みであれば、「マイクロチップ装着証明書」が渡されます。マイクロチップ装着証明書は、飼い主情報が変わった際には変更手続きが義務付けられています。
保護施設から確認をとり、忘れずに手続きを行いましょう。これは「うちの子」となるための、とても大切な手続きです。
4.ワクチン接種歴の証明書を確認する
いつ、どこで、何種のワクチンを接種したのかを保護施設に確認しましょう。証明書は必ずもらえるはずです。
ちなみに、わが家の猫は3種混合ワクチンを接種していました。
猫の3種混合ワクチンとは?
・猫伝染性鼻気管炎
・猫カリシウイルス感染症
・猫汎白血球減少症(猫パルボウイルス感染症)
以上の3つの感染症を予防するためのワクチンです。
完全室内飼育の場合は、毎年接種する必要がないと考える獣医師もいます。飼い主さんの考え方もさまざまで、3年に1回程度と考える方も多いようです。
愛猫の健康状態に応じて、かかりつけの獣医師に相談しましょう。
また、ペットホテル利用時や保険加入時には、ワクチン接種の証明書が必要になることがあります。
5.動物病院にかかる前に考えておきたいこと
日々の生活に必要な食事やトイレ用品はもちろんのこと、猫の体調変化により医療費も必須です。突発的な出費として医療費も考慮しておきましょう。
ペット保険の加入も検討しておくと安心です。
猫は環境の変化に弱く、ストレスから体調を崩すこともあります。そして、里親として猫を迎えた初日は、丸一日ご飯を食べないことも珍しくありません。
そのため、すぐに動物病院に連れて行ける準備も必要です。いざという時の備えとして、ペット保険に加入していると安心ですね。
保護施設によっては、保険の代理店になっているケースもあるので、相談してみると良いでしょう。ご自身のライフスタイルに合わせて検討してみてください。
関連記事>> 猫のペット保険は本当に必要?迷ったときの考え方とおすすめ3社比較
6.まずは動物病院で健康診断を受けよう
2代目猫のタルタルを迎えた時、保護施設の方からは「健康そのもの!」と太鼓判を押されたので、安心して猫を迎え入れたました。
ところが、最後に健康診断を受けたのは「わが家に来る2年前」でした!
保護施設の方針や事情があるとは思いますが、タルタルの場合は「きっと大丈夫だろう」と判断されたのかもしれません(定かではありませんが…)
先代猫の保護主さんに状況を相談したところ、すぐにでも健康診断が必要では?という判断になりました。
※我が家の2代目猫の場合は極端な例かもしれませんが、猫の状態により出迎えてから直ぐの健康診断は安心にもつながりますね!
健康診断で判明した、うちの子の病気とは?
2代目猫・タルタルの健康診断で明らかになったのは「シュウ酸カルシウム」でした。

シュウ酸カルシウムって何?
猫のシュウ酸カルシウムとは、尿が酸性に傾くと結石ができやすい病気で、水分不足やストレス、食事などさまざまな要因が関係しています。
詳しいことは↓のサイトをご参照ください。
猫の尿石症(尿路結石症)ってどんな病気?
猫はストレスを感じると水を飲む量が増えると聞いていたので、タルタルの場合も環境変化による影響だと思い込んでいましたが、それは私の思い込みでした。
現在は療法食を取り入れて、経過観察中です。
関連記事>> 【体験版】ユリナリーS/Oって実際にどうなの?~尿疾患系の療法食について~
さらに、健康診断では「マラセチア外耳炎」も見つかりました。

マラセチア外耳炎とは…?
耳の中にいる常在菌(マラセチア)が増えすぎることで炎症を起こし、かゆみや耳の中の汚れ、黒っぽい耳垢などがみられます。
うちに来た当時、タルタルの耳の中を軽く綿棒で触れると、黒っぽい耳垢がびっしり…!すぐに点耳薬を処方してもらい、こちらは完治しました。
加えて、軽い歯肉炎や歯石も見つかっています。
若くて見た目が元気そうでも油断は禁物です!隠れた病気が潜んでいる場合も少なくありません。だからこそ、保護猫を迎えたら一度しっかり健康診断を受けさせてあげることが大切です。
保護猫を迎えるための6つの行動で確認すべき書類
保護猫を迎えたら「やっておきたい6つの行動」を進める中で、保護施設から猫を迎える際には書類手続きも伴います。
大変だと感じるかもしれませんが、ひとつずつクリアしていけば大丈夫!その先には、猫との幸せな毎日が続いていくのです。
代表的なものは以下の通りです。
✔ 猫の保険加入のための資料請求と確認(加入する場合のみ)
✔ 保護施設に支払う費用の請求書の確認
✔ ワクチン接種証明書
✔ マイクロチップ装着証明書
以上、保護施設から猫を迎える際に渡される、または確認すべき書類となります。
まとめ
保護猫を迎える前の準備から、実際に迎える日まで―――
実際にやることは多いですが、段階を踏んで行動すれば大丈夫です。ここはぜひ、頑張って乗り越えましょう!
保護猫を迎える時に必要なものって何?こちらの記事も参考までに!
関連記事>> 【保存版】保護猫を迎えるときに必要なものと快適に暮らすためのポイント