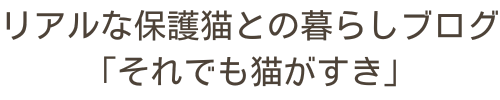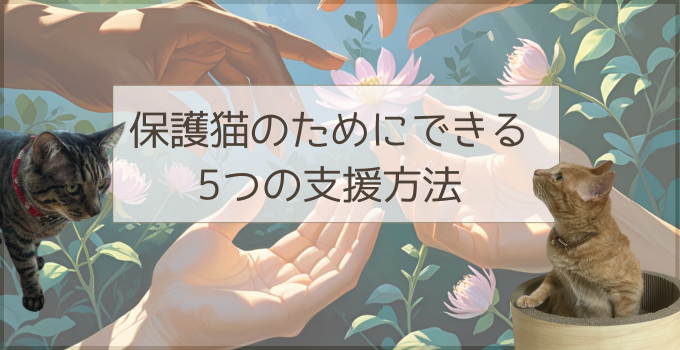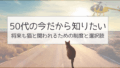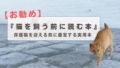「猫は好きだけど、事情があって飼えない」——
そんな気持ちを抱えてはいませんか?
私自身の話になりますが、初代猫・ハーにゃんを見送った時は心にぽっかりと穴が開き、深いペットロスに陥っていました。
「もう二度と猫なんて飼わない」と当時は強く思ったものです。
それが今では、「ハーにゃんの命を無駄にしたくない」という思いが、私を支援活動へと向かわせてくれました。
この記事では、保護猫のためにできる支援の輪を少しでも広げたいという思いを込めて——
猫が飼えなくてもできる5つの保護猫支援の方法についてお話しします。
猫のためにできる「活動支援」5つの方法
猫を飼う以外にもできる、5つの行動があります。
2. 支援物資の提供
3. SNSでシェア&「いいね」
4. チャリティーイベントの参加&グッズの購入
5. クラウドファンディングでのプロジェクト支援
それでは順番に見ていきましょう。
🐾【1】毎月少額からはじめる「寄付」
寄付は、保護猫支援の中でも手軽で続けやすい方法ですが、寄付先は慎重に選ぶ必要があります。
ポイントは大きく分けて3つです。
📌 写真などで状況が分かるようにし、透明性のある活動報告がされているか
📌 実績があるかどうか(保護数や譲渡数などが報告され、透明性があるか)
私が実際に使っている保護猫への寄付サイト
北海道であれば「しっぽの会」や「ツキネコ北海道」が有名で間違いないですが、インターネットには全国多岐に渡って、多くの保護団体が存在しています。
寄付先選びのポイントを確認しても正直、本当に信頼できるかどうか見定めるのは難しいです。そこで、私が利用しているサイトが「アニマル・ドネーション」という寄付サイトです。
アニマル・ドネーションでは審査を通過した団体だけが登録されており、寄付金の使い道にも透明性があります。
44の認定団体すべてに寄付したり、あるいは特定の団体だけを寄付することもできます。
また、毎月寄付するのもよし。その他、「〇〇団体を今月限定で寄付する」方法も選択できます。
自分の予算とペースで支援できるので、無理なく継続しやすいです。
🌐公式サイト:公益社団法人アニマル・ドネーション
🧺【2】支援物資の提供
保護団体では常に、物資の支援も呼びかけています。
特に喜ばれる物は以下の通りです。
毛布や使用済みタオル
使用済みのタオルなどはOKであっても、衛生面を考えると比較的良い状態の物が好ましいです。毛布やタオルは、特に子猫や高齢猫に使えます!
防寒のために使用したり、体を拭いたりと、使い道は多岐に渡るので重宝します。
消耗品(猫砂・ペットシーツなど)
猫たちが生活する上では欠かせないのが消耗品です。猫砂は毎日使用するので欠かせません。保護猫が多数いると消費も大量となり、費用の負担も大きくなります。
ペットシーツもトイレの失敗などに使えるので、大変喜ばれます。
フード
保護猫は病気を持っている場合も多く、できれば栄養価の高いフードが重宝がられます。子猫や高齢猫は特に、栄養価の高いフードが良いでしょう。
また、口腔内に問題があっても、食べやすいウェットフードが重宝します。
Amazonの「ほしい物リスト」からの支援方法
多くの団体がAmazonの「ほしい物リスト」を公開しています。
Amazonの支援プログラムを通じて、必要な物資を直接届けることができるシステムです。Amazonのほしい物リストをのぞくだけでも、立派な一歩になります。
🌐保護犬・保護猫 支援プログラム
💬【3】SNSでのシェア&「いいね」
SNSでのシェアや「いいね」でなにができるのだろう?
そんな疑問ありませんか?
大丈夫です!実は情報の拡散は大きな力になります。
里親募集のリポスト
活動報告に「いいね」する
たったこれだけのこと。
SNSを普段使いしている人であれば、日常で負担なくできる支援です。
まずは1つの投稿をシェアするところから始めてみませんか?
🎁【4】チャリティーイベントへの参加&グッズ購入で応援
イベントに参加する
チャリティーグッズを買う
楽しみながらできる行動が支援となり、保護猫を支える力に繋がります。
「猫を飼う予定もないし、譲渡会に行く意味ないよね」そんなふうに思っていませんか?
実は、グッズを購入したり、イベント会場で寄付するだけでも立派な支援になります。譲渡を考えていなくても、気軽に足を運んでみてください。
※ただし、長居はせず猫たちのストレスに配慮を。
💡【5】クラウドファンディングでのプロジェクト支援
大がかりな医療費や施設修繕など、大きな資金が必要な時に活躍するのがクラウドファンディングです。
保護猫関連のプロジェクトも多く、気になる案件だけを選んで支援できます。少額から自分の予算に応じて支援できるので、負担も少なく続けやすいです。
🌐保護猫関連のプロジェクト一覧(READYFOR)
おわりに
私は子どもの頃からずっと、犬や猫が大好き!
これまで保護犬・保護猫と暮らすことで、「救っていた」つもりが、今では「救われている」と常々、思っています。
動物にまつわる残虐なニュースを見聞きするたびに、悔しくてやり場のない思いもしますが、多くの小さな支援が大きな力となり、すべての犬猫の幸せに繋がることを切に願っています。
猫が飼えないからこそ、できる支援があります。無理のない範囲で、「あなたにもできる保護猫支援」を今日から始めてみませんか?
小さな思いやりが、猫たちの未来を変える力になると信じて。
🐾あわせて読みたい:
50代の今だから知りたい|将来も猫と関われるための制度と選択肢